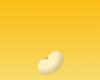|
適材適所
2007年9月12日
自然農はすごい、どんなところでも誰でもこれでお米ができる!
数年前では、そう思っていた。 実際それまでの中山間地での自然農では、みなうまくいっていた。 今の家のまわりでお米を作り始める前までは・・・。 この山の中での田んぼを始めてからは、場所によっては耕さざるを得ないことを痛感する。 ここ、平生町長谷という部落は、水がこんこんとわき出て、水のおいしいところ。 うちの家も2本の沢にはさまれて、水にはまったく苦労しない。 だが、地面の下を無数の水の道があるのだろう。 そこかしこに大きな穴があいている。 田んぼの下にも、床土の下に大きな穴がいくつもあるのだろう。 田植えをして水をためたとたん、毎年のように大穴があく。 大きい時は僕の背よりも深く、中に入って踊れるくらいの大穴。 おまけに砂の多い砂質土なので、不耕起の場合、水を入れても入れても全く水のたまらないところも多い。 いわゆる「ざる田」、それも超がつく。 2,3年自然農で作ってみたが、水をごうごうと入れっぱなしにしてやっと端まで水がいく。だけどその下の段には、水は届かない。 そして超冷たい山の水。 おまけに日照時間も短く、稲の分けつが、里の半分以下だった。 それに必ずどこかに大穴があいてはその補修にすごい労力を使うという始末。 里での米作りにくらべて、手間も労力も神経も、3倍以上かかった。 しかも収穫は半分以下。 というわけで、一昨年から耕すことにした。 耕すと何とか水はたまり、次の田にも水が落ちるようになり、水持ちがいいから、水をじゃんじゃん流し込まないですむ。 そうすると、水温も上がり、稲の成長はすすむ。 さて、そうして耕しはじめた僕だが、やっぱり自然農にもっていきたい。 一度耕せば穴もふさがり、不耕起でいけるんじゃないかと一枚の田をまた自然農にした。 去年、不耕起1年目。 稲刈り前に一部に大穴があいたが、なんとかお米にはなった。 そして今年2年目。 現状は写真の通りだ。 2年で元のざる田に戻ってしまった。 田植え後、中の方まで全く水が届いてなかったのだ。 畦には水がたまっていたから、水は入ってるもんだと僕もすっかり安心していたのがいけなかった。 しかも今年の6月はほとんど雨も降らなかった。 で、中の方に植えた苗は、気づいたときにはみな消えていた。 ここはうちに自然農を習いにきたみんなが植えた田だっただけに、申し訳なかった。 いつもなら7月の頭には、稲の姿がくっきり見え始めるのに、どうもおかしいなと思って気がついたのが、7月半ば。 すでに取り返しがつかない時期でした。 来年はここもやっぱり耕します。 一生懸命植えられた方、ごめんなさいです。 それでも、一部、水があった所の稲は、すくすくと成長してくれています。 今ちょうど赤米の穂が出穂したところ。 というわけで、今現在の僕の考えとしては、耕さずにすむところは、耕さずにやるのが一番いいけど、耕した方がいいところもあるんだなというのが正直なところ。 田んぼは耕すものと思い込んでることも愚なら、耕すを悪として耕さずを善とするのも愚ってことかな。 要はとらわれず、その場その時に応じて、施せる、それが大事なことのようです。 |