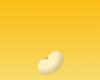薪は三度人を暖める
2004年3月2日
「薪は三度人を暖める」といいます。
一度目は、薪を割るとき。
二度目は、燃やした火にあたるとき。
そして三度目は、その火で調理した料理を食べるとき。
パコーーン!!
斧を振り下ろした瞬間、薪の音が山にこだまする。
この瞬間の気持ちよさといったら、やった人しかわからない。
僕がはじめて薪を割ったのは、もう10年前。
熊本、阿蘇山に住んでいたとき。
手に血豆をつくりながらも、薪割りの気持ちよさにはまっていった。
時間がたつごとに、着ていたシャツが一枚、また一枚と脱ぎ捨てられていく。
ケニアでも、炭焼きに携わり、やっぱり薪を割ることが多かった。
そして今、我が家のまわりは、割られるのを待つ木々たちでいっぱいだ。
クヌギ、カシ、リンゴ、・・・・。
木にはそれぞれ独特の香りがあることも最近知った。
リンゴの木は、甘い香りがする。
そしてリンゴの木を燃やしてつくる料理も、あまいリンゴの香りがほのかにするのだ。
ピッとボタンを押せば、すぐに暖まる電気や灯油のストーブと違い、薪ストーブは火をつけるのにも手間がかかる。
薪の火は簡単にはおきてくれない。
火をおこすには、それなりの知恵と技術が要求される。
どんな薪を使うか、太さは?、並べ方は?・・・。
火をつけるのも着火剤を使えば簡単だろうが、僕はなるべく使わない。
着火剤に頼らず火をおこすと、素直にうれしいからだ。
僕の小さなこだわりは、ティッシュ一枚で火をつけること。
割り箸を何本にも割ったような細い木から、少しずつ少しずつ、火を大きくしていくのだ。
それは子どもや稲の成長と似ている。
どのようにすれば炎が大きく、持続するかを考え、手を差し出さねばならない。
ほっておきすぎても、手を出しすぎても、火は消えてしまうことがある。
しかし一旦炎が安定したら、そこからは優雅な時がながれていく。
ゆらめく炎は、見ていて飽きることがない。
そして体は、芯から暖まっていくのだ。
それは灯油や電気のストーブとは、暖まり方の次元が違う。
結婚してからというものの、料理という料理をほとんどしたことのない僕だが、
薪ストーブを置いてから、人が来るときには、ピザを焼くのが定番になった。
電気やガスで、オーブンをわざわざ暖めるのと違って、
勝手に暖まってるんだから、使わないほうがもったいない。
オーブンは、魔法の箱だ。
とにかく入れておけば、なんでもとびきりの味に化ける。
さつまいも、じゃがいも、りんご、とうもろこし、パン・・・。
これを料理と呼ぶのかどうかは知らないが、とにかく美味くなるのだ。
そしてストーブの上では、水をいれた鉄瓶があっという間に蒸気をあげる。
ついでにいえば、我が家の薪は「三度」でなく、「四度」僕らを暖めてくれる。
湯たんぽだ。
空いたスペースに、湯たんぽを乗せておけば、
冬の冷たい夜も、ふとんの中はポッカポカの夢ごこち。
暖をとる、火をながめる、薪のはぜる音を聞く、そしてほのかに香る木のにおい・・・。
この魅力的な焚き火を、家の中で毎日できるというのは、幸せだと思う。
それにしてもなぜ、炭や薪などの炎は、こんなにも僕らを惹きつけるのだろう。
火を囲み、火と共に暮らしてきた祖先たちの記憶。
僕らのDNAに刻み込まれたその何万年もの記憶が、刺激されるのだろうか。
今夜も子どもたちと、外で焚き火をした。
厳寒の冬空に星がきらめく。
真っ赤な炎が舞い上がり、オレンジ色に照らされた二人の子どもたちの顔。
その小さな4つの瞳が光り輝く。
「コンコン、コンコン!!」
2歳になる娘が、空を指差す。
舞い降りてくる灰が、雪に見えたのか。
本物の火のある暮らし。
それは人の心をも暖めます。
一度目は、薪を割るとき。
二度目は、燃やした火にあたるとき。
そして三度目は、その火で調理した料理を食べるとき。
パコーーン!!
斧を振り下ろした瞬間、薪の音が山にこだまする。
この瞬間の気持ちよさといったら、やった人しかわからない。
僕がはじめて薪を割ったのは、もう10年前。
熊本、阿蘇山に住んでいたとき。
手に血豆をつくりながらも、薪割りの気持ちよさにはまっていった。
時間がたつごとに、着ていたシャツが一枚、また一枚と脱ぎ捨てられていく。
ケニアでも、炭焼きに携わり、やっぱり薪を割ることが多かった。
そして今、我が家のまわりは、割られるのを待つ木々たちでいっぱいだ。
クヌギ、カシ、リンゴ、・・・・。
木にはそれぞれ独特の香りがあることも最近知った。
リンゴの木は、甘い香りがする。
そしてリンゴの木を燃やしてつくる料理も、あまいリンゴの香りがほのかにするのだ。
ピッとボタンを押せば、すぐに暖まる電気や灯油のストーブと違い、薪ストーブは火をつけるのにも手間がかかる。
薪の火は簡単にはおきてくれない。
火をおこすには、それなりの知恵と技術が要求される。
どんな薪を使うか、太さは?、並べ方は?・・・。
火をつけるのも着火剤を使えば簡単だろうが、僕はなるべく使わない。
着火剤に頼らず火をおこすと、素直にうれしいからだ。
僕の小さなこだわりは、ティッシュ一枚で火をつけること。
割り箸を何本にも割ったような細い木から、少しずつ少しずつ、火を大きくしていくのだ。
それは子どもや稲の成長と似ている。
どのようにすれば炎が大きく、持続するかを考え、手を差し出さねばならない。
ほっておきすぎても、手を出しすぎても、火は消えてしまうことがある。
しかし一旦炎が安定したら、そこからは優雅な時がながれていく。
ゆらめく炎は、見ていて飽きることがない。
そして体は、芯から暖まっていくのだ。
それは灯油や電気のストーブとは、暖まり方の次元が違う。
結婚してからというものの、料理という料理をほとんどしたことのない僕だが、
薪ストーブを置いてから、人が来るときには、ピザを焼くのが定番になった。
電気やガスで、オーブンをわざわざ暖めるのと違って、
勝手に暖まってるんだから、使わないほうがもったいない。
オーブンは、魔法の箱だ。
とにかく入れておけば、なんでもとびきりの味に化ける。
さつまいも、じゃがいも、りんご、とうもろこし、パン・・・。
これを料理と呼ぶのかどうかは知らないが、とにかく美味くなるのだ。
そしてストーブの上では、水をいれた鉄瓶があっという間に蒸気をあげる。
ついでにいえば、我が家の薪は「三度」でなく、「四度」僕らを暖めてくれる。
湯たんぽだ。
空いたスペースに、湯たんぽを乗せておけば、
冬の冷たい夜も、ふとんの中はポッカポカの夢ごこち。
暖をとる、火をながめる、薪のはぜる音を聞く、そしてほのかに香る木のにおい・・・。
この魅力的な焚き火を、家の中で毎日できるというのは、幸せだと思う。
それにしてもなぜ、炭や薪などの炎は、こんなにも僕らを惹きつけるのだろう。
火を囲み、火と共に暮らしてきた祖先たちの記憶。
僕らのDNAに刻み込まれたその何万年もの記憶が、刺激されるのだろうか。
今夜も子どもたちと、外で焚き火をした。
厳寒の冬空に星がきらめく。
真っ赤な炎が舞い上がり、オレンジ色に照らされた二人の子どもたちの顔。
その小さな4つの瞳が光り輝く。
「コンコン、コンコン!!」
2歳になる娘が、空を指差す。
舞い降りてくる灰が、雪に見えたのか。
本物の火のある暮らし。
それは人の心をも暖めます。